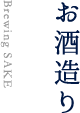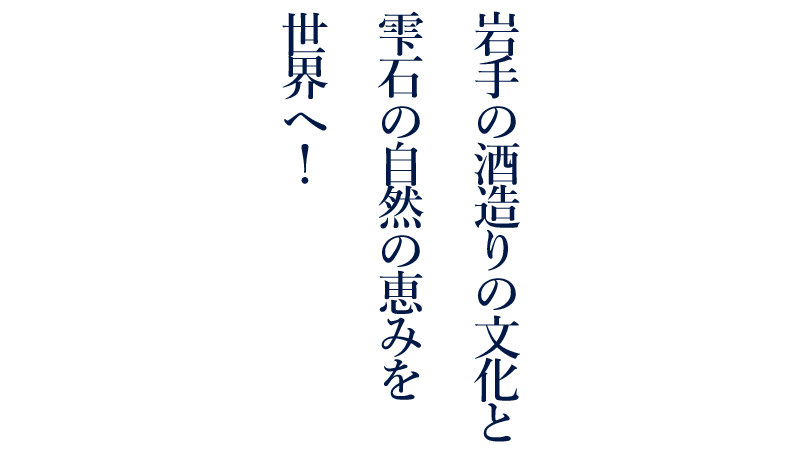

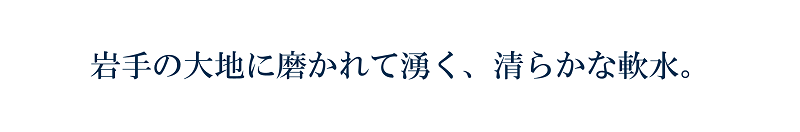
菊の司酒造の真裏を流れる中津川は年間を通して川底が煌めく、穏やかな清流です。夏はアユ釣り、秋にはサケが産卵のため遡上し、冬は白鳥が飛来します。当蔵では中津川の伏流に湧く水を井戸で汲み上げ仕込水として利用しております。岩手の大地に磨かれた水は、適度なミネラル分を含みながらも水質は軟水。この仕込水こそ、お米の味わいを引き出し、丁寧に低温発酵させるための当蔵の命の水です。


菊の司酒造がある岩手県は、昔からお米が育てにくいといわれる土地でした。夏はやませという冷風が吹き、米を登熟させにくいためです。しかし、長年の研究による品種改良と栽培技術の向上によって、現在では全国と十分に渡り合える品質の優れたお米がたくさん収穫できるようになっています。岩手県の代表する酒米「吟ぎんが」「ぎんおとめ」「結の香」を軸に、当蔵ではお酒造りに使用する原料米の90%以上を地元産のお米を使用しています。また、契約栽培にも取り組んでおり、情熱溢れる農家さんと「お米づくり」から挑戦しています。全国区の「山田錦」や「亀の尾」「愛山」「雄町」などは全て信頼できるルートから品質の良いものだけを仕入れています。

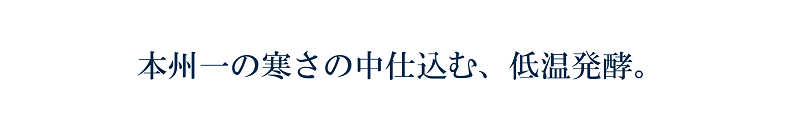
菊の司酒造がある岩手県盛岡市は、本州一の寒さで知られる北国です。雪は少なく、二つの山脈に囲まれた盆地の真冬は、日中の気温が氷点下ということもめずらしくありません。当蔵ではそんな寒さと軟水の仕込み水を活かした酒造りを磨き続けております。軟水仕込みはお米の味わいを引き出しやすく、じっくりと3週間強低温発酵させることで香りの鮮やかな、メリハリのある日本酒に仕上げることができます。華やかながらも味わいに芯があり、甘味のほかに酸味、苦味、渋味がバランスよく感じられます。また、当蔵のお酒はキレがよく、お食事との相性が良いとのご評価も頂戴しております。
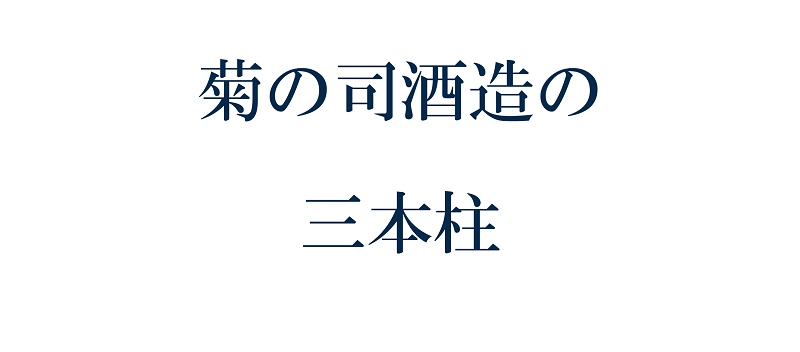
当蔵では槽から搾り出た直後の日本酒の味わいを損なわずにお楽しみいただくため、貯蔵環境にもこだわっております。酒質矯正のための炭素ろ過等は一切行わず、原酒で5日以内に火入れ、瓶詰めに取り組んでいます。
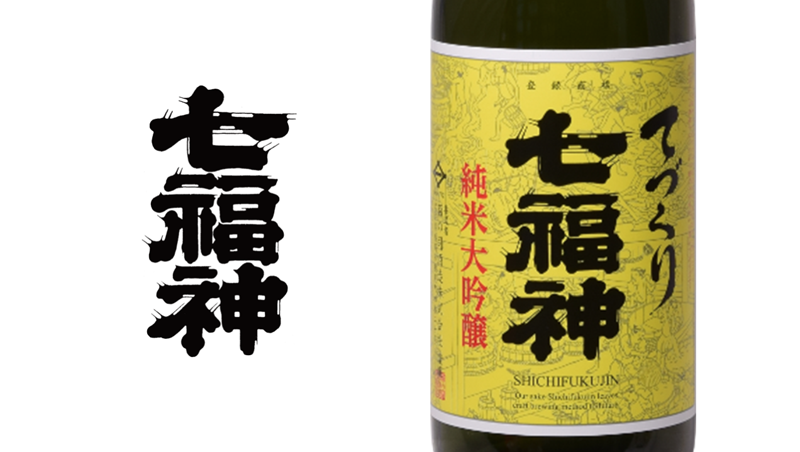
南部杜氏のふるさと石鳥谷で醸す箱庄酒造店との合併の際に引き継いだ銘柄が「七福神」です。吟醸酒の先駆け「てづくり七福神」は半世紀を越えて三世代に愛される、当蔵の看板商品のひとつ。南部流を基本とした淡麗な酒質が特徴。
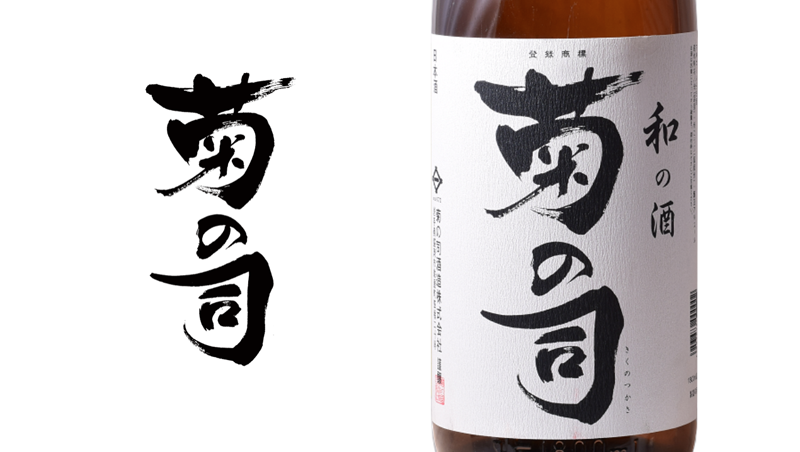
地元内外で広くご愛顧いただいている当蔵の幹となっているのが「菊の司」です。香味のバランスを重視し、冷酒からお燗まで、普段の晩酌で親しみやすいラインナップを揃えております。
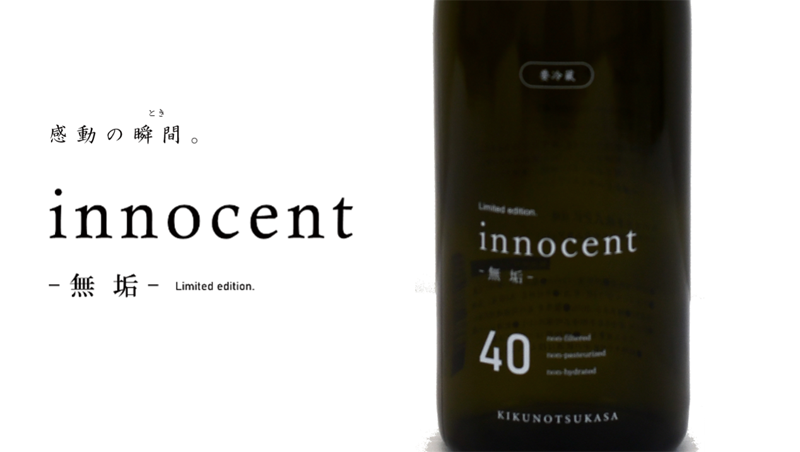
岩手県酒造好適米を丁寧に低温発酵させた搾りたての無垢な無濾過生原酒の味わいをお楽しみいただくコンセプトシリーズ。吟醸香と甘味が絶妙に絡み合った重厚なボディとフィニッシュの爽快感のコントラストをご堪能ください。